アーユルヴェーダとは?

アーユルヴェーダと聞いても、ご想像がつかない方は沢山いらっしゃると思います。
アーユルヴェーダとはインド・スリランカで5000年以上前から伝統的に行われてきた最も古い医学のひとつです。
アーユル(又はアーユス・Ayus/生命)は、サンスクリット語で『生命』『寿命』、ヴェーダ(Veda/科学)は、『科学』『真理』を意味します。
よって、アーユルヴェーダとは『生命科学』と訳され、病気の予防、さらには健康の維持増進や若返り(アンチエイジング)を目的とした、まさに「生命の科学」、言い換えれば『生きるための法則』、『長生きする方法』です。
スリランカのアーユルヴェーダ医師に『アーユルヴェーダをひとことで言うと?』と質問した時、帰ってきた言葉は『よく生きること』。
5000年の歴史を持つ『よりよく生きるための知恵・教え』それがアーユルヴェーダです。
アーユルヴェーダの治療は、病気を診るのではなく、『人』を診るといいます。

熱があるときは解熱剤、下痢は下痢止めというように、症状のみを治療する現代の医療(対処療法=西洋医学)に対し、アーユルヴェーダ医師が患者さんに対する最初の質問は、『あなたはどのような体質ですか?』です。
治療は個人個人のオーダーメイドで、ひとつの病気でもすべての人に効くという薬は無く、すべての人に良い治療は無い、と考えます。
病気の治療だけではなく、予防、健康の維持、長寿を目的とし、さらにはより良く生きる、至福に満ちた人生を送ることを目指します。
アーユルヴェーダの教えは健康に生きるためのもので、心身の力を蓄え、免疫力を高めるように働きかけます。

病気の発症には病原菌やウィルスだけでなく、肉体(患者)も重要な要因です。菌やウィルスと闘うのが現代医療だとすれば、アーユルヴェーダは肉体である『人』を対象とします。
インフルエンザがどんなに流行してもかからない人もいます。
ウィルスだけで病気になるのではなく、受け入れる側にも要因があり、病気が一方的にやって来るのではなく、人が病気を選択していると考えることもできます。
病気にならないからだをつくることは、どんな病気があらわれても対処することができるとアーユルヴェーダは教えています。
個々の身体と心の状態を簡単な言語で説明し、自然治癒力を高めて、生きる知恵を教えてくれるものと言っても過言ではありません。
アーユルヴェーダを知っていくと、そのほとんどが日常生活に関係する事であり、身近なものだという事がわかってきます。
アーユルヴェーダは、『からだを支配するのは心である』、つまりバランスの取れた心の状態がより高い健康を創造すると考え、至福に満ちた心身の健康、病気の治療と予防のための方法について、医師の手によるものから生活習慣の提案まで、広範囲の教えを説く伝統医学なのです。
日本では、まだ認知度の低いアーユルヴェーダですが、WHO(世界保健機構)が正式に奨励している代替医療の一つでもあります。
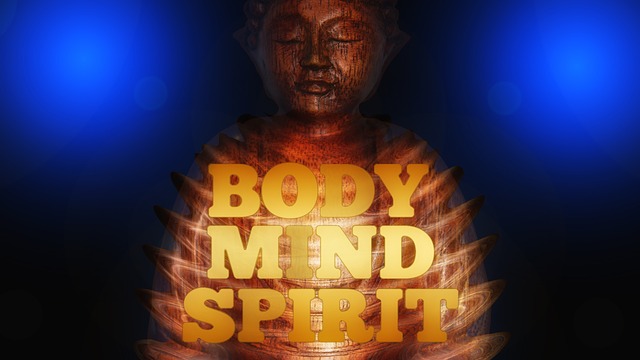
アーユルヴェーダの体質
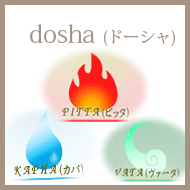
アーユルヴェーダでは、「ドーシャ」と呼ばれる3つの要素「ヴァーダ」「ピッタ」「カパ」が私たちの心身の健康を支配していると考えています。
また、この3要素(3つのドーシャ)のバランスによって一人ひとりの体質がきまり、その中で最も多くもっているドーシャを、アーユルヴェーダではその人の『体質』とみなします。
例えば、ヴァータ体質の人はヴァータ・ドーシャを多く持ち、ヴァータの属性である軽・冷・動などが、心身の特徴です。どちらかというと痩せ型で背が高く、頭の回転が速く、いつも動きまわっているタイプです。
最も多く持っているドーシャは最も増えやすく、バランスを崩しやすいドーシャです。例えば、ヴァータの人はヴァータが増えやすく、手足が冷えやすかったり、ちょっとしたことが心配で眠れなくなったりしますが、これはヴァータが増えた時に起こりやすい現象です。
体質(ドーシャのバランス)は卵子と精子の受精時に決定されると考えられ、生まれてから死ぬまで、その人の心身の健康、ライフスタイル、人生に関与します。生まれ持ったもの、両親の持つ体質、環境等の要因が体質を決定づけますが。生まれた時の体質が永遠であるか否かについてはいろいろな説があります。
不調が生じたとき、体質ごとに対処法が異なるので、まずは、自分のドーシャバランスを知ることが大切です。
ご自分のタイプを知って、健康増進に役立てましょう。
アーユルヴェーダで使用するオイル

アーユルヴェーダのオイルトリートメント(アビヤンガ)には、 どんな施術があるのか、また施術にはどんなオイルが使われているのかあげてみます。
- ゴマ油・ココナッツ油・ヒマワリ油・ヒマシ油などの植物油
- 多くの薬草(ハーブ)
- ヤギの乳などの動物性の材料で作られた特別の油(ギー)
体を温め、老化を防ぐゴマ油の威力

アーユルヴェーダの施設では、各症状に合わせた薬用オイルが使われますが、私たちが普段、使いやすいのは「ゴマ油」です。
なんとなく中華料理の香ばしい匂いを思い出すかもしれませんが、あれは『焙煎ゴマ油』です。
マッサージで使うのは、いわゆる『太白ゴマ油』。
こちらは無色透明でほとんど匂いもありません。
ゴマ油は殆どの薬用オイルのベースオイルとして使われています。皮膚からも早く吸収され、体内組織の細部まで浸透しやすい性質を持っています。
体を温める効果もあるので、冷え性の方、寒い季節には大いに活躍してくれます。
様々なオイルの中でも抗酸化作用がとても高く、一度熱処理をすることでさらにアンチエイジング、若返りの効果も高まります。
アーユルヴェーダにおけるマッサージの目的は、次の9つです。

- 血行促進
- 毒素排出
- 免疫系システムの強化
- 骨格・筋肉を柔軟にする
- 活力の増強
- 集中力を高める
- 若返り
- 心身のリラクゼーション
- ヴァータの鎮静
以下のような場合はマッサージを避けて下さい
- 食事の直後
- 感染症にかかっているとき
- 熱があるとき
- 皮膚に感染する病気があるとき
- 静脈瘤
- 高血圧
- 肺病
- 生理中
※マッサージは朝または日中温かい時間に行うことが効果的といわれています。
入浴後、身体が温まっているときもよいでしょう。
※食前はよいですが、食後は少なくとも1時間はあけて下さい。
※血圧が極端に高いときは、マッサージは避けたほうがよいでしょう。
少し高めという程度の場合は、ゆっくりとした速度で行うマッサージがお勧めです。
※妊娠3カ月まではマッサージは控えたほうがよいでしょう。
3カ月を過ぎ6カ月までは背中、頭、腰、脚(足裏や甲も)は行いません。
6カ月以降は背中、脚、肩のみならマッサージしても構いません。
産後はマッサージをするのは60日を過ぎてからにしましょう。
